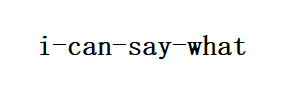あなたが考える、都市に対する帰属感とは何ですか
大学から大学院まで、ある都市から別の都市へ、春と秋が巡り、4 年とそれに続く 3 年が過ぎました。時々学校の片隅をぶらぶら歩くと、「帰属感」という言葉を思い出します。友人と感慨を述べることがあります。ここでは、私はずっと帰属感を見つけられなかったような気がします。
大学から大学院まで、ある都市から別の都市へ、春と秋が巡り、4 年とそれに続く 3 年が過ぎました。
時々学校の片隅をぶらぶら歩くと、「帰属感」という言葉を思い出します。
友人と感慨を述べることがあります。ここでは、私はずっと帰属感を見つけられなかったような気がします。
私が考える帰属感とは、この都市が寛容さと暖かさ、愛に満ちており、私が一歩一歩着実かつ安心して歩めることだと思っていました。
しかし、不満なことに遭遇することが多く、価値観の一致しない人と付き合うことや、様々な奇妙な規則や制度にも困惑します。
そして、私がここで過ごす大部分の時間は平凡で、コロナ禍により多くの計画が狂い、学業面での自由放任的な指導のため、私はよく頭の中が真っ白になっていろいろなところを探し回っていました。
私はどうすればいいのか、未来はどうなるのか?私もしばしば悲観的になります。
しかし、これらのことを振り切って、友人たちと集まり、街の道をのんびりと散歩し、空に大きなオレンジ色の夕焼けが漂っているのを見ると、この都市がとても素敵だと思います。
悩み事があり、焦りを感じるときは、立ち去ってしまえます。なぜなら、私のさまよう魂を収める場所があり、友人が自ら作った料理を味わえ、夜遅くまで心配せずに語り明かせることを知っているからです。
このような瞬間がたくさんあり、私は再びこの都市が大好きになります。
この都市は私が出会いたい人と出会わせ、大切な人を私のそばに残してくれました。
この見知らぬ都市に友人がいる限り、私には少しずつ帰属感が芽生えます。
後になってわかったのですが、生活の大部分の時間はこのように平凡で退屈で、言うに値しないものばかりでした。
しかし、多分日本の絵本作家・佐野洋子が『神も仏もいない』の中で書いているように、「それぞれの今にはそれぞれの喜びがある。どんなに辛い瞬間でも、人は小さな喜びによって生きていける。生活のコツは、小さな喜びをたくさん見つけることにある」のでしょう。
だから、この都市で起こるすべてのことは期待に値し、いつも小さな素敵なことに出会え、小さな喜びを残せるのです。賈平凹は『老西安』の中で、「私はしばしば考える。都市とは何か。コンクリートの山と混雑した人群なのだろうか。私たちが自転車通勤族のとき、私たちは自家用車やタクシーが自転車道をひっかくように走り回るのに反感を抱く。しかし、私たちがお金があってタクシーを利用できるようになり、甚だしくは自家用車を持つようになると、自転車に乗る人が車の道を塞ぐのが嫌になる」と書いています。
確かに、人生の異なる段階では、異なる悩みがあります。それは都市とは関係ありません。
都市は決して老いません。老いるのは私たちだけで、私たちは絶えず歩き、絶えず経験し、時々刻々と微かに老いていくのです。人によっては去り、人によっては残ります。ここで苦しんでも、嫌悪しても。ここは私の最も青春的で自由な時光を占めており、また同じように、私の成長のある軌跡を傍観者の目で見続けてきたのです。
それも私が残したいものです。ある夜、私は歩道橋に立ち、この都市の夜を見つめました。賑やかな人々を見て、ネオンが輝くビルを見て、この人の波の中で何人かと出会い、これからは、この都市の冷たさと暖かさがすべて自分と関係があることを知りました。
見下ろすと、世界は灯火輝き、一人一人が自分のかすかな光でこの都市を明かりにしようと努力しています。
私は欄干にもたれてぼーっとしながら、ここに残って好きな生活を送れる未来を夢見ました。
冒頭の問題に戻りますが、私はわかりました。いわゆる帰属感とは、この都市の友人、天候、経験した出来事などによって形成されるものなのです。
私にとって、ある都市の帰属感とは、この土地に、自分を最も大切な存在として扱ってくれる人が一人か数人いて、自分がこの世界と一人で向き合っているわけではないことを教えてくれることで、私に一か所に根を張る勇気が与えられることなのです。
そして、私はまた、他人に追随する必要はなく、自分の心に従えばいいこともわかりました。この世界は広大で、望む遠方は自分で辿り着かなければならないのです。